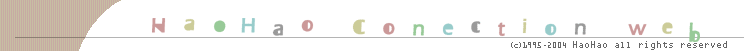|
十時半ごろ橋本は一人で嘉義米羔に向かった。朝食はお決まりの豆漿油條コンビだったので、それほど空腹でもなかったし、不満でもなかったが、その店は午前中しか営業していない、今日のこの機会を逃せばもう二度と食べられないかもしれない、ということをテルミに力説してようやくホテルを出してもらえた。
____なんでいちいちお伺いをたてにゃあかんのか…。
からだのことを考えてくれているんだということは勿論承知しているが、自分が肉類を食べないからといってそれを強要されるのはかなわないと橋本は思う。テルミにそう言えば、ひとこと「たべすぎ!」とかたずけられるに違ないから、下手に出ておくほうが得策だ。
線路沿いに十分ほど西に歩くと見えてきた高架の下を、ここでいいのだろうかと迷いながらもくぐりさらに五分ほど歩くと、ようやくそれらしい店が現われた。朝五時から営業しているらしいので、この時間帯は暇なのか、それともいくら台灣だからといって、朝の十一時前からこんなものは食べないのか、客は一人もいず、親父はぽつねんと調理場に立ってそぼそぼと降る雨を眺めている。
その店はおんボロという表現がぴったりあてはまるような店構えだった。店というより四阿といったほうがよいかもしれない。屋根はトタン張り、壁などというものは存在せず柱と屋根だけで成立している。だからいけないのかというと、それがまたよい味を出しているのではなかろうかと橋本は思う。良く言えば、商売なんかはこれだけで充分だというような潔さが、その建造物にはあった。
橋本がいくぶん緊張しつつ店に入ろうとすると、年のころなら自分とほぼ同じと思われる女が何の迷いもなくすーと店に入って行く。やはり評判どおりのうまい店なのかもしれないと、橋本は腹のなかで喜んだ。橋本には見ただけでは味を想像できないプリンのようなものを女は注文した。
壁に貼ってある菜単の中から、頭に叩き込んでいたその文字をゆびさし、指を一本立てて親父に注文した。そんな変わった注文の仕方をしても親父は、万事心得ている様子でカフェのギャルソンのようにあくまで静かに頷いて、大きな鍋の蓋を開けた。
運ばれて来たそれは、子供用みたいに小さな飯茶碗に、米が軽く盛られ、上には肉そぼろみたいなものが品よく載っかっている。
____うまい・・・・・・。
一口食べて、橋本はわが身のしあわせを噛み締めた。米は餅米のようだ。肉の出汁も米にかなり染み込んでいる。親父が遅れて運んでくれたスープも、あっさりとしていて申し分がない。
____おかわりをするとまた叱言をくらうかもしれない・・・・・・。
なに、構うものか。ちらと妻の顔を思い浮かべていると、男が一人入って来てスープのようなものを注文し、さらに橋本が頼んだものも注文した。それを見てから、橋本は食べ終わったお茶碗を親父のところに持って行き、もういちど指を一本立てた。
柱の間から見る外はまだ雨が降りやんでいない。昨日も思い出した映画監督の映像が再び橋本の脳裏に映し出される。
「えっ・・・?」
ぼんやりしている間に、女が橋本の机の前に来て何かを言ったようだった。どうやらそこに置いてある新聞を持って行ってもいいか、と言っているようだ。えーとか、あーとか曖昧な返事をして、どうぞというような仕草をすると、女はどうもとも言わずに新聞を自分の席に持って行き、ばさっと広げた。当たり前だが紙面は漢字ばかりで組まれているからか、それを読んでいる人間をも威圧的な印象にさせるのかもしれないけれど、基本的にこの女には無為草堂や日月潭教師会館の小姐にあったものがないに決まっている、と橋本は柄にもなく考察した。
____うまかった・・・・・・。
もしテルミを無理に連れて来ていたら、おかわりはできなかったろうな、と思いながらポケットをまさぐっていると、男が先にごちそうさんというようなことを言い、お金を払いに立った。すると、女が素早く立ち上がり男の食べ残したスープの具を、どこからとりだしたのかビニール袋に流し込んだ。
____これは一体・・・・・・?
と思っていると、男と女はドイツ製の車に仲良く乗り込んだ。やはり世の中はよくわからないで満ちている。橋本はゆっくりと席を立ちあがった。
「ばかっ」
部屋に帰ると、いきなり橋本はテルミに叱られた。
____おかわりをしたのがばれたのか・・・・・・?
「ど、ど、どうしてなのかな?ぼ、ぼ、ぼくにはわ、わ、わからないんだな」
そうちょっとおどけて探りをいれる。
「どうして、早く帰ってこなかったのよ。フロントから早くチェックアウトしてくれって、催促の電話があったのよ。それなのに、自動販売機なんかひょこひょこ見てっ」
実はこの前から気になっていた、あちこちで見かける銘柄の缶コーヒーを、口直しに飲んでみるかなと、つい駅前の自動販売機を物色してしまったのだ。
「どうしてそれを・・・・・・」
「ここから見てると、あなたは一目瞭然なのよ。そんな大きな形をしてオーバーオールなんか着ているのなんかあなた一人だけよ。それなのにうれしそーに、わっはっはっていう感じで歩いてるのよ、わかってるの?」
「・・・・・・・・・・・・・・・・」
幸いにも、そこに目当てのものはなかったので、これ以上の叱言を言われることは免れたようだ。火車の時間は昼をだいぶ回っているので、今日はゆっくりできる。だからぎりぎりまでねばってもよかろうと、フロントには十一時四十五分にチェックアウトすると言っておいたはずなのに、と思いながら橋本はのそのそと荷物をまとめだした。
____さすがにもう食べられない・・・・・・。
妻に付き合って観世音素食に入ったけれど、餅米が今ごろになってきいてきたらしく、きのうの意気込みもどこへやら、橋本は何も頼んでいない。することもないので店内を見回していると、曰く付きの例の缶コーヒーを発見した。おやおやと言って、妻に恐る恐るお伺いをたてると、一人だけで箸を動かすのに少し遠慮を覚えるのか、めずらしく許可が出た。橋本がタクシーを否定するようにテルミは缶飲料をはじめとする一連のからだにわるそうなものを認めていない立場をとっている。しかしベジタリアンレストランに置いてあるものだから、自然指向の飲みものなのかもしれない。レジで二十元を支払い、一口含むと懐かしいような甘いコーヒー牛乳の味が橋本の口にひろがった。
|